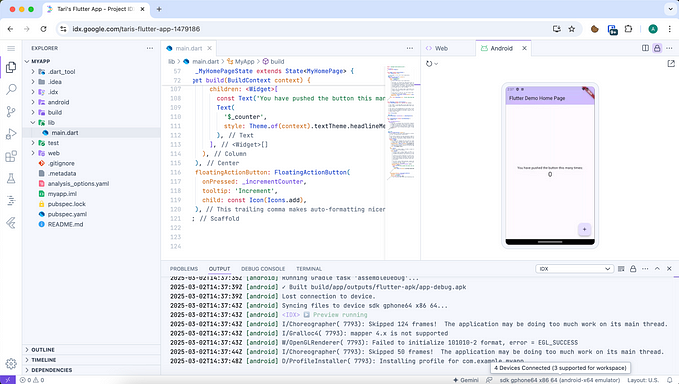自然災害を「人類共通の敵」とする HRTF②:病院船

日本の「病院船」がもつ可能性
日本政府は2020年度第一次補正予算で7,000万円の「病院船」調査費を計上している。軍隊が保有する病院船は、紛争地帯の軍人だけが対象ではなく、大規模自然災害におけるHA/DR(人道支援・災害救援)に使われることも多い。世界の病院船では米海軍の「マーシー」と「コンフォート」が有名だが、これらの船は最近ではニューヨークとロサンジェルスに派遣され、コロナウィルス感染者治療の支援に当っている。日本の病院船構想は東日本大震災後に提起された。しかし、2013年の内閣府調査報告書では、建造費、効果的な運用、運営費、医療スタッフの迅速かつ長期的な確保などの問題点が指摘され、導入に至らなかった経緯がある。今回の再提案は感染症対策を含むもので、超党派議員連盟によれば、その運用は海上自衛隊等を含む「病院船保有機構」で行うとしている。
軍隊が保有する狭義の「病院船」に対する攻撃はジュネーブ条約で戦争犯罪として禁止されている。国際法に守られた白地に赤十字、赤新月、赤ひし形シンボルの力は大きい。しかし自衛隊は軍隊ではないはずだからジュネーブ第2条約22条「軍用病院船」にはできない。加えて、紛争が多発する現代において、ジュネーブ諸条約が想定するような国家間の紛争、あるいは湾岸戦争のような国連安保理授権の武力行使は少ない。その反対に、9.11後に米国によって戦争とされた、いわゆるテロとの戦いや、国内外の武力紛争が続いている。こうした安心して暮らせない地域の拡大に加えて、頻発する大規模自然災害は、身をまもる術を持たないもっとも弱い人口、国内外の貧困層を直撃している。日本がこの時期に病院船導入を検討するならば、少なくとも数十年単位で病院船を支えるビジョンを持つ必要があると思われる。まさにそれが「自然災害を人類共通の敵」と捉えて、多国籍部隊が民・軍で連携するHRTF構想だ。
軍の存在意義が問われる中での、人道支援・災害救援(HA/DR)の広がり
2011年3月11日の東日本大震災において、24 の国・地域及び5つの国際機関から緊急援助隊等が日本に派遣された他、16 か国 43 のNGOが来日した。126 の国・地域・国際機関からの支援物資や寄付金は総額 175 億円以上となった。また在日米軍と自衛隊の連携 した「トモダチ作戦」では、最大人員約 2万 4,500 名、艦船 24 隻、航空機 189 機などが投入された。(外交防衛委員会調査室)
一国だけでの対応が難しい大規模自然災害が起こった時、被災72時間以内に人道支援・災害救援の緊急展開ができるかどうかに多くの命がかかっている。そして、今のところこうした緊急展開能力、自己完結能力を持って初期対応が可能なのは軍事組織だけだ。一刻が争われる人道支援・災害救援(HA/DR:Humanitarian Assistance, Desester Relief)をいかに展開するか、そしてどのように長期的な復興、医療支援につなげて行くかについては被災国を中心とした多国間の協力、軍事組織と非軍事、民間組織との協力関係が不可欠であり、平時から協力の枠組みを作り、同じ釜の飯を食って訓練をしておくことが望ましい。東日本大震災で、日本は被災国として大規模なHA/DRを受益側から経験した。この経験を東アジアの信頼醸成につなげるために、今後はICRC赤十字国際委員会が2008年に発行した「国際的な災害救援および初期復興支援の国内における円滑化および規制のためのガイドライン」、HA/DRに係る各国の枠組みなどを精査し、国際連合人道問題調整事務所(OCHA)と共に多国間の協力関係を作る枠組みをとしてスタートさせるべきだ。日本の「病院船」はその契機となり得ると考えている。
「病院船保有機構」の国際化
HRTFを日本から実現する第一歩は「病院船保有機構」をジュネーブ第二条約第25条に規定する「中立国救済団体の病院船」とし、多国間協力による運用に道を開くことだ。具体的には、病院船保有機構を国際条約に基づいて設置し、併せて多国間及び民軍の協力関係を定める。HRTF構想については前回書いたが、一言でいえば自然災害を「人類共通の敵」と捉える人道支援部隊(Humanitarian Relief Task Force)である。地球温暖化による自然災害は増える一方で、日本でも今まで経験したことがないような水害に見舞われている。HRTFは、東日本大震災で日本が経験したHA/DR分野で、東アジアに常設の国際機関を作る構想である。今後とも米中の緊張が高まることが予想される中で、こうした信頼醸成と紛争予防の分野で日本が果たすべき役割は大きい。
HRTF構想は2009年当時、東京外国語大学大学院平和構築と紛争予防講座伊勢崎研究室の特別客員研究員だったデズモンド・マロイ Desmond Molloy 氏のチームに私の事務所が依頼して作ったものだ。マロイ氏はアイルランド国軍大尉としてレバノン国連平和維持軍、カンボジア国連軍事監視団に参加、退役後はシエラレオネ、ハイチで国連PKOの武装解除の責任者などを務めた。また、UNDP国連開発計画DDR(Disarmament, Demobilization, Reintegration:武装解除・動員解除・社会復帰)担当シニア・アドバイザーでもあった。伊勢崎賢治氏やデスモンド・マロイ氏のように、DDRの現場を知り尽くしている人は少ない。HRTFはそうした貴重な批判精神を反響板にして構想された。そうはいっても、現在のところこの構想は予算に裏打ちされた政府の提言からは程遠いところにある。ごまめの歯軋り、蟷螂(とうろう)の斧に間違いないが、机上の空論や現実味のない夢物語ではない。東アジアの国々にとって緊張緩和、信頼醸成につながる話であって、政治の世界から本気で取り組めば必ず実現できるはずだ。足りないのは政治的意思なのである。しかし、こうした提案を日本から行う前に準備すべきことがある。それが日米地位協定の改正であると思う。(HRTF③へ)